日本フードコーディネーター協会理事の伊藤裕美子です。
皆さんは、お店でどうやって飲む日本酒を決めていますか?
私は、料理と合わせて飲みたいので、まずはラベルに書かれている「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」の表示や、使っているお米の種類から推測される味わいで選びます。
日本酒は同じ酒蔵でも全くちがうと感じることも多いのです。
不思議ですね。
第2回では少しでも選ぶ時の参考になればと日本酒の酒類について書きます。

瓶やメニュー表記から読み取れるものとして、日本酒は大きく分けて「純米酒」「吟醸酒」「本醸造酒」の3つに別れます。
まず、「①純米酒」と「②吟醸酒」「③本醸造酒」の違いですが、これは、後者には醸造アルコールを使用しており、この点の違いだけです。「え?お米だけじゃなく、別のアルコールを入れているの?」と不審に思うかもしれませんが、いえいえ、それぞれに違いがでて、個性的な味わいが生まれます。
初めに「①純米酒」ですが、お米と麹とお水だけで作っていますので、お米本来の味が楽しめます。
酒米には「山田錦」「雄町」「亀の尾」「五百万石」などたくさんあります。
ちなみに私は、軸の太さを感じられる「オマチスト(雄町米が好きな人)」です。
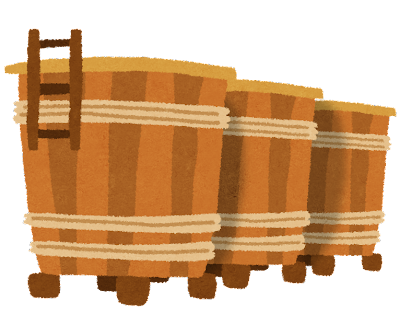
「②吟醸酒」は「吟醸造り」と言う磨いたお米を、通常よりも低い温度で長時間発酵させる方法で作られたお酒です。
この「吟醸づくり」によって、固有の香りが生み出されます。
みなさんも山形の「十四代」という銘柄は聞いたことがあると思います。
「十四代」は吟醸酒のもつ、フルーティで華やかな香りで人気となったお酒です。
先日「十四代」の飲み比べをしました。
同じ吟醸酒でも、火入をしない「生詰」「無濾過生詰」垂れ酒の「大吟醸酒」と3種類頂きましたが、違う味わいが楽しめました。
「②吟醸酒」と「③本醸造酒」は、何が違うかというと「精米歩合」です。
「②吟醸酒」は精米歩合が60%以下のものです。
吟醸造りの中でも「大吟醸酒」と表記されているものは50%以下と決められています。
それに対して、「本醸造酒」は「精米歩合」が70%以下となっていますので、比較的リーズナブルに楽しめます。
「本醸造酒」の中にも「特別本醸造」と言われるものは吟醸造りではないけれど、精米歩合が60%ですので雑味の少ないクリアな味わいになります。
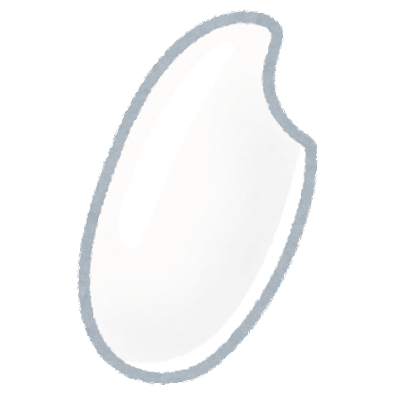
ここで出てくる「精米歩合」とは数字が小さくなるほどお米の外側が削られていると言うことを表します。
50%とは外側から5割削っている、70%は3割だけ削っているということです。
外側の雑味のもとになる部分を削って小さくしています。
次回は、食べ物との組み合わせの話をしますね。
今宵は、干物に辛口の「純米酒(熱燗)」で楽しみたいと思います。ふふふ
<(3)に続きます>
日本酒のお話(3)は12月公開予定です。
